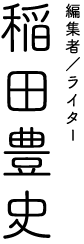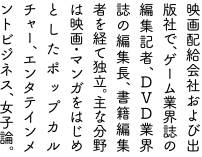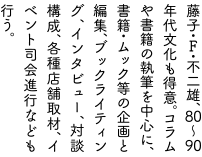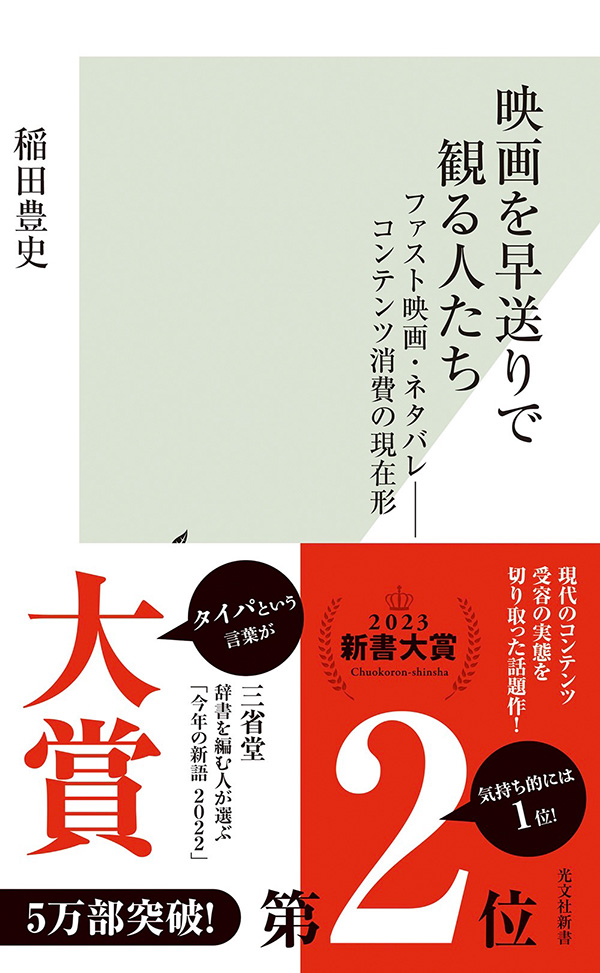コラム再録『頭文字D』――初出『V.A』2006年1月号
- 2013.05.04
こじつけの極致といった文章です!
—————————————————————————————-
日本は不思議な国だ。なぜこの国の電気街では、近代イギリスの女性使用人(メイド)がパーツ屋のチラシを配っているのか。なぜ牛丼屋にTVクルーが詰めかけて、「最後の一杯」を食したサラリーマンにコメントを求めるのか。そしてなぜ、カーブだらけの峠道を百分の一秒でも速く走ることに、そこまでの情熱を傾けられるのか。
直線の少ない峠道を最速で抜けるために必要なのは、最高速ではなく、スムーズなカーブの通過だ。その「スピードを落とさずにカーブを曲がる操車上の技術」のことをドリフトと言う。車体が横にスライドしながら急カーブに滑り込む、アレだ。主人公・藤原拓海は、峠で豆腐の配達を繰り返すうち、神業的なドリフト技術を身に付ける。ほどなくして、「藤原とうふ店」の文字が刻まれた名車ハチロク(AE86)が、秋名山の伝説としてライバルたちを蹴散らしてゆく――。
F1のように整備されたレース場を周回するわけでも、ラリーのように大自然を疾走するわけでもない。一般道をただ走るだけの何が楽しいのか?
しかし、メイドを性的モチーフに、ファーストフード屋をメロドラマの舞台に見立てられる、日本人の素晴らしい想像力をもってすれば、「ドリフト」が「青春」の比喩であることにも気付くはずだ。スピードという大切なものを抱きしめたままでカーブを駆け抜けるためには、「乗り心地」や「安全」といった、手を離さなければならない快適さが山ほどある。そこに生じる転倒寸前の危うさこそが、青春だ。手は2本しかない。片方がハンドルを握るなら、残った方は何を掴むのか。こういう禅問答のような見立てが必要だったからこそ、本作はハリウッドではなく、我々と精神性の近いアジア人たちの手で映画化されたに違いない。
劇中、拓海は予感する。何かを選ぶことは、何かを捨てることなのだと。シフトレバーを握れば、助手席の女に手は回せない。究極的には、そういうことだ。(了)
- コラムアーカイブ
- 02:00:25